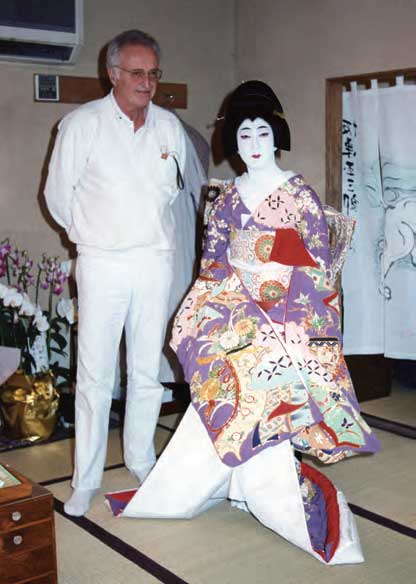伝統芸能としての歌舞伎
福井 本年、生誕250 周年を迎えたベートーヴェンは、「芸術は長く、生命は短いというが、長いのは生命だけで、芸術は短い」という言葉を残したと言われています。生み出された芸術作品が輝いている期間は、実はそれほど長くないという意味で発せられたこの言葉は、数百年前の名曲が消えることなく輝き続けている現代においては、「素晴らしい芸術は永遠に語り継がれるものであるが、その奇跡の恩恵にあずかれる芸術は少ない」と解釈することもできます。そこで、玉三郎先生には日本の伝統芸能の伝承についてのお考えをお聞かせ願いたいのですが、以前先生は、「日本の芸能は、非常に削ぎ落とされた端正なものである。歌舞伎なり能なり、日本ほど口伝えで人間同士が引き継いできた国は珍しい」と、ご発言されています。
玉三郎 そうですね。西洋音楽にとって、その解釈はそれぞれの時代の、それぞれの演奏家によるとはいえ、譜面が残っていたことが伝承という観点から言うと、とても良かったのではないでしょうか。その点、歌舞伎は、江戸時代の初期に民衆の中から生まれたものが明治には天覧になり、伝統芸能となっていったのですが、書き伝えられたものはあったものの、譜面のようにしっかりとした形では残っておらず、どこか曖昧なところがあります。伝わり方が口伝えであった分、難しい部分があった。その過程において、変わっていってしまうわけですね。
福井 前々号でお話を伺った落語の桂文治師匠も、落語について同じことをおっしゃっていました。
玉三郎 歌舞伎は、その時点時点で、「付け加え」たり「削ぎ落とし」たりして、境目で揺れながら作られてきました。したがって、そういった伝統を役者がどう捉えるかが重要、ということになります。長い時代の中で、必要なものが付け加えられ、要らないと思ったものが省かれてきたという点では良いのですが、しかし一方でいわゆる「形骸化」を引き起こす恐れが生じます。
福井 役の性根を表現せずに硬直化し、文字通り形ばかりのものになってしまう危険があると。
玉三郎 そうです。したがって、自分自身が形骸化しているか否か、その判断を役者がしっかりした上で演じることが、とても大切です。また、それさえしっかりしていれば、やはり長い歴史を持つ演目の方が皆さんに受け入れられやすいでしょう。長いことやってきた中で、皆さんの共感を得られないものは、消滅していったわけですから。音楽が歴史上で、良いものだけが残ってきたことと同じことです。
福井 長い時をかけ、演出や演技の流れも伝承されて磨き上げられた古典の演目。それらの「形骸化していない」継承こそが、古典芸能としての歌舞伎の根幹ということですね。

板東玉三郎特別招聘教授による特別講座
「継承」と「創造」
福井 一方で、玉三郎先生は「現代のお客様に、伝統芸能としての純粋なままの歌舞伎をお見せすることに難しさを感じる」とおっしゃっています。
玉三郎 はい。しかし、いまのお客様に来ていただかないと成立しないものだと思います。いまお客様に喜んでいただけなかったら、私たちの芸術、舞台は時間を越せないんです。
福井 私が昨年末鑑賞した新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』も、そういう視点に立ったもの、つまり時代に即した新しい世界の創造ですね。
玉三郎 そうです。ナウシカのファンの方たちを呼び入れるという点においては、貴重な試みだと思います。実際、歌舞伎自体がそうやって出来てきたのですから。歌舞伎は、出雲阿国(いずものおくに)(注:安土桃山時代から江戸時代に活躍した女性芸能者)から始まったと言われています。
福井 出雲阿国が歌舞伎の原点とされる「歌舞伎踊り」を初めて演じたのが、いまから400 年以上前の1603 年。西洋音楽で言えば、ルネサンス期の終わりから、次のバロック期への過渡期にあたると考えると、歌舞伎の有する歴史性を実感します。
玉三郎 阿国も念仏を唱えて踊るというところから始まり、お客様の支持を得て、そこで自分が作りたいもの、したいことをやりだしたのでしょう。皆さんに目を向けていただき、足を運んでいただき、その力を借りて自分の目指すところに進んでいったということだと思います。
福井 「創造をし続けることも歌舞伎の伝統」と聞いたことがあります。優れた新作は再演を重ねて練り上げられ、やがて新たな古典となって、次世代へ継承されるのですね。「継承」と「創造」は、一見相反するように見えますが、歌舞伎の発展に欠かせない両輪なのでしょう。

小さな機械の問題点
福井 いまの話に関連するかもしれませんが、クラシック音楽界にも、客層が高齢者に偏っているという危機感があります。若者離れの状態が続くと、音楽家を志す人間も増えない。それでなくても現代には娯楽があふれています。そうした中で、音楽や舞台といった、時と場所を限定した瞬間芸術というものが、今後どのようになっていくとお考えでしょうか。
玉三郎 難しいですね。一番問題なのは、昨今はスマートフォンなどの「小さな機械」で聴いて良しとしてしまうこと。小さな機械で聴いて、それで本物を体験したと誤解してしまうことです。本物のコンサートホールで聴いたような気になってしまう、その勘違いが一番難しいところですね。
福井 音大生も、玉石混交ともいえるYouTube などで聴くことが多く、もうCD はあまり聴かないですね。そのCDすら、生音ではないのですが。なかなか演奏会まではたどり着きにくい。だからこそ、大学の先生の指導が重要になると思います。
玉三郎 生の音、実音にどれだけ触れるかということですね。実音ではないものを聴いて、実音はどういうものか興味を抱くきっかけになっていただければ良いのですが、そこがつながらないというのが問題点だと思います。ただ一方で、パソコンであったり、スマホであったりというものが“飽和状態”になって、近年は実音を志向する若者が少しずつ増えてきているような気もしています。そうした人たちがいる限り、自分を見失わずにしっかりやっていればこちらに目を向けてくれるし、耳を傾けてくれるのではないでしょうか。実際、歌舞伎界でも、能楽界でも、落語界でも、クラシック音楽界でも、若者を取り込もうということは、最初からやっていたと思うんです。
福井 その時代、時代で、そういった試行錯誤が重ねられてきたのでしょうね。
玉三郎 ただ、若者だけに分かってもらうのではなく、究極は万人に分かってもらうことを目指すべき。誰に向かって作るのか、どの世代に向かって作っていくのかというのは、あまり考えない方がいいと思います。例えば雑誌の場合は、今どういう層に読まれているのかを聞いて、じゃあその年代に向けて発信しましょう、というのはあるでしょう。でも自分の芸術作品を、ある世代に合わせるなんてことは出来ないと思うんです。

福井 おっしゃる通りです。ただただ、真理を追求するということですね。何かの本で読んだのですが、玉三郎先生はいわゆる「上下関係」というものがあまりお好きではない。上の人に言われたからではなく、誰に言われたかが大事だと。
玉三郎 そう思います。ただ、上下関係での礼儀作法は当然あります。人間が生まれて成長して、年寄りになっていく中での上下関係というものは無視できないものなんだと思います。けれど、ものを作るという上での真髄、本当の魂、力というものは、上下、前後、左右では考えられない。

板東玉三郎特別招聘教授による特別講座
福井 それはスポーツでも何でも同じですね。日常の礼儀はあるけれど、いざ試合が始まったり、幕が開けば、そんなことは関係ないと。遠慮などしていられない。
玉三郎 本当の自分の芸術的精神というものは、(上下などの)位置ではないです。
福井 作曲家だって、先輩に遠慮して曲を書くわけでもないでしょう(笑)。
玉三郎 そういう人もいたでしょうが(笑)。でも、彼らがどの世代に向かって曲を作ったなんてことはないでしょう。
福井 だからこそ、それらの音楽がもつ普遍性が存在するのだと思います。ただ、作曲家たちが、偉大なる先人たちの作品を大いに分析したことは間違いないです。
玉三郎 それはそうでしょうね。
福井 登場人物の悲しみや喜びを共にし、時代を経ても変わらない人間の姿に感動する──これこそが優れた歌舞伎作品に触れる醍醐味であり、傑作と呼ばれる音楽作品を聴いたときに感じる幸福感と同様なのでしょう。